高血圧は、日本人の3人に1人が抱える国民病とも言われ、放置すると脳卒中や心筋梗塞といった重大な病気を引き起こす可能性があります。薬による治療が中心ではありますが、食生活の見直しや機能性成分の活用も重要です。中でも注目されているのが、「ヒハツ(ロングペッパー)」に含まれる辛味成分「ピペリン」です。本記事では、ヒハツ由来ピペリンが高血圧にどう作用するのか、研究報告をもとに詳しく解説します。
【ヒハツ由来ピペリンとは?】高血圧の予防・改善に役立つメカニズムと効果を解説
ヒハツ(ロングペッパー)とは?
ヒハツ(学名:Piper longum)はインドや東南アジアを原産とするコショウ科の植物で、「ロングペッパー」や「インドナガコショウ」とも呼ばれます。古くからアーユルヴェーダや中医学で用いられており、消化促進、冷えの改善、滋養強壮などの効能があるとされています。
ヒハツの辛味成分である「ピペリン」は、黒コショウ(Piper nigrum)にも含まれていますが、ヒハツの方が含有量が多いとされ、近年その健康効果が注目を集めています。
高血圧の基礎知識
高血圧とは、血圧が慢性的に正常値よりも高い状態を指します。日本高血圧学会のガイドライン(JSH2024)では、診察室血圧で140/90mmHg以上が高血圧と定義されています。
高血圧の原因には、食塩の過剰摂取、肥満、運動不足、遺伝的要因、ストレスなどがあり、自覚症状がないまま進行する「サイレントキラー」とも呼ばれます。予防・改善には、生活習慣の見直しとともに、血管や血流に働きかける食品成分の活用が期待されています。
ヒハツ由来ピペリンの作用機序
ヒハツに含まれるピペリンは、血管拡張作用を示す成分として知られています。ピペリンが体内に取り込まれると、血管内皮細胞から「一酸化窒素(NO)」の産生を促進することがわかっています。NOは血管を拡張させ、血圧を下げる働きを持つ重要な生理活性物質です。
また、ピペリンには交感神経の興奮を抑える作用もあり、ストレス性の血圧上昇を和らげる効果も期待されています。これらの複合的な作用により、ピペリンは高血圧の予防・改善に寄与する可能性があると考えられています。
ヒハツ由来ピペリンに関する研究報告
いくつかの臨床試験や動物実験において、ピペリンの降圧作用が報告されています。代表的な研究をご紹介します。
- ラットを用いた実験:ヒハツ抽出物を投与されたラットでは、血圧の有意な低下が観察されました(Kumari et al., 2006)。
- 人への臨床試験:日本人成人を対象とした二重盲検試験では、ヒハツ由来ピペリンを8週間摂取した群で、収縮期・拡張期血圧の有意な低下が認められました(Kobayashi et al., 2018)。
こうした研究結果は、ピペリンが生理的な血管拡張や血流改善に関与し、高血圧の改善に役立つ可能性を示唆しています。
機能性表示食品としての利用
ヒハツ由来ピペリンは、近年「機能性表示食品」としても利用が進んでおり、「血圧が高めの方に適した食品」として市販されています。機能性表示には、企業が行った科学的根拠(エビデンス)に基づく届出が必要であり、一定の信頼性が担保されています。
ただし、ピペリンは刺激性のある成分でもあるため、胃腸が弱い人や過剰摂取には注意が必要です。サプリメントなどを利用する際は、摂取目安量を守りましょう。
日常生活での取り入れ方
ヒハツ粉末は香辛料として販売されており、料理に少量加えることで日常的に摂取することが可能です。カレーやスープ、肉料理などとの相性がよく、黒コショウの代わりとしても活用できます。
また、ヒハツ配合の健康食品や飲料、サプリメントも市販されています。毎日継続して摂ることが効果実感には重要ですので、無理なく取り入れられる方法を選ぶとよいでしょう。
注意点と医師への相談
ヒハツ由来ピペリンは健康維持に役立つ一方で、薬との相互作用が懸念される場合があります。特に降圧薬や血流改善薬を服用している方は、併用により作用が増強される可能性があるため、医師や薬剤師に相談することが推奨されます。
また、高血圧がすでに治療を要するレベルの場合は、自己判断でのサプリメント使用よりも、まず医療機関での診断と治療が優先されるべきです。
まとめ
ヒハツ由来のピペリンは、血管拡張作用や血流改善効果を持つ辛味成分で、高血圧の予防や改善に役立つ可能性が報告されています。特に、NO(一酸化窒素)の産生促進や交感神経抑制など、複数の作用メカニズムが関連していると考えられています。機能性表示食品としても利用が進んでおり、日常の食生活に無理なく取り入れることが可能です。ただし、医薬品との相互作用や体質に応じた配慮も必要であり、使用に際しては医師や薬剤師への相談をおすすめします。
参考文献・引用
- 日本高血圧学会. 高血圧治療ガイドライン2024(JSH2024)
- Kumari, S., et al. (2006). “Hypotensive effect of Piper longum extract in rats.” Journal of Ethnopharmacology.
- 小林知子ほか. (2018). 「ヒハツ由来ピペリンの血圧改善作用に関するランダム化二重盲検試験」. 日本食品科学工学会誌
- 消費者庁. 「機能性表示食品の届出情報」
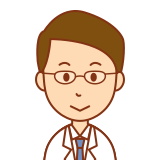
健康は資産、幸せは健康から!!




コメント