コレステロールが高いと、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが高まります。健康診断の結果に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そんな中、注目を集めている成分が「リコピン」です。リコピンは、トマトなどに多く含まれる赤い色素で、抗酸化作用をはじめとした健康効果が報告されています。本記事では、リコピンがどのようにコレステロールに作用するのか、科学的根拠や摂取方法も含めて詳しく解説します。
リコピンで悪玉コレステロールを減らせる?トマトの健康パワーとその効果を解説
リコピンとは?
リコピン(Lycopene)は、カロテノイドという天然色素の一種で、主にトマトやスイカ、ピンクグレープフルーツなどの赤色の野菜や果物に多く含まれています。中でもトマトはリコピンの代表的な供給源で、加工品であるトマトジュースやトマトソースなどにも豊富に含まれています。
リコピンの最大の特徴は強力な抗酸化作用です。活性酸素を除去する働きがあり、細胞の老化や生活習慣病の予防に役立つとされています。
コレステロールとは?
コレステロールは、脂質の一種で、細胞膜の構成成分やホルモンの材料として体にとって必要不可欠な物質です。しかし、過剰になると動脈硬化などの原因となります。
- LDLコレステロール(悪玉):血管内にコレステロールを運び、過剰になると血管に蓄積されます。
- HDLコレステロール(善玉):余分なコレステロールを回収して肝臓に運びます。
このうち、問題となるのがLDLコレステロールの増加です。リコピンがこのLDLに対してどう作用するのか、次に見ていきましょう。
リコピンがLDLコレステロールに与える影響
いくつかの研究では、リコピンの摂取がLDLコレステロールの酸化を抑制することが示されています。酸化されたLDLは動脈硬化の引き金となるため、リコピンの抗酸化作用は非常に重要です。
臨床研究の例
2011年に発表されたメタアナリシス(Ried et al.)では、リコピンを1日25mg以上摂取することで、LDLコレステロールが約10%低下したと報告されています。
また、トマトジュースを1日200ml、12週間摂取したところ、LDLコレステロール値の改善が見られたという報告もあります(Fuhrman et al., 2000)。
リコピンの効果的な摂取方法
リコピンは脂溶性の成分であるため、油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。生のトマトよりも、加熱されたトマト加工品の方が吸収されやすいのも特徴です。
- トマトソースを使ったパスタ
- オリーブオイルをかけたトマトサラダ
- トマトスープ、ミネストローネ
また、サプリメントとしてリコピンを摂取する方法もありますが、まずは食品からの摂取が推奨されます。
注意点と副作用
リコピンは基本的に安全性の高い成分ですが、サプリメントで過剰摂取した場合、皮膚がオレンジ色に変色する「リコペニア」と呼ばれる症状が出ることがあります。食品からの摂取であれば問題ありません。
リコピンとコレステロール改善に関するQ&A
- Q. トマトを毎日食べればコレステロールは下がりますか?
- A. トマトを継続的に摂取することでLDLコレステロールの酸化を抑える効果が期待されますが、劇的な改善には医師の指導や生活習慣の見直しも必要です。
- Q. どのくらいの量を摂取すれば良いですか?
- A. 目安としては1日25mgのリコピン摂取が有効とされており、トマトジュース200mlやトマト2~3個で補えます。
まとめ
リコピンは、抗酸化作用によりLDLコレステロールの酸化を抑える働きがあるため、動脈硬化の予防に寄与するとされています。特に、加熱されたトマト製品や油と一緒に摂取することで、その吸収率は格段に高まります。コレステロール値が気になる方は、日々の食事にリコピンを取り入れてみてはいかがでしょうか。ただし、改善には継続的な生活習慣の見直しも欠かせません。
参考文献・引用
- Ried, K., Fakler, P., & Stocks, N. P. (2011). Lycopene reduces systolic blood pressure and LDL cholesterol: A systematic review and meta-analysis of intervention trials. Maturitas, 68(4), 299-310.
- Fuhrman, B., Elis, A., & Aviram, M. (2000). Hypocholesterolemic effect of lycopene and β-carotene on serum lipid profile and LDL oxidation. Atherosclerosis, 149(2), 287–294.
- 厚生労働省「e-ヘルスネット」
- 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版」
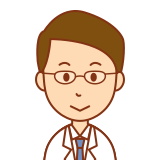
健康は資産、幸せは健康から!!

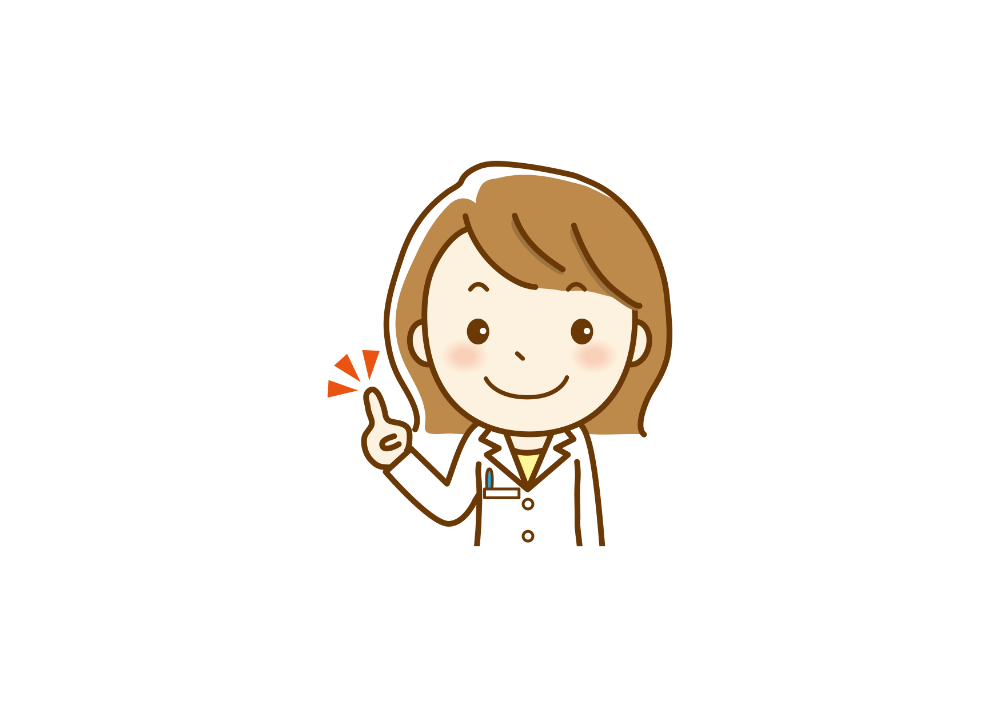


コメント