ビタミンDは「骨のビタミン」という印象が強いかもしれません。しかし、近年の研究では、ビタミンDが免疫機能の調整に深く関わり、風邪やインフルエンザ、感染症対策においても重要な役割を果たすことが明らかになっています。一方、日本人の多くがビタミンD不足とされ、現代人にとって見過ごせない健康課題のひとつです。
この記事では、ビタミンDと免疫力の関係、最新研究によるエビデンス、食品やサプリを通じた効果的な摂取方法についてわかりやすく解説します。
ビタミンDと免疫力の関係とは?不足が招くリスクと効果的な摂取方法を解説
ビタミンDとは?基本的な役割
ビタミンDは脂溶性ビタミンの一種で、カルシウムの吸収を助けて骨や歯の形成を支える栄養素として知られています。しかし近年、ビタミンDは免疫細胞の働きを調整する役割があることがわかり、注目を集めています。
体内のビタミンDは、食品から摂取するほか、日光を浴びることで皮膚で合成されます。ところが現代人は屋内で過ごす時間の増加や紫外線対策の徹底により、慢性的な不足が指摘されています。
ビタミンDと免疫細胞の関係
免疫には体外から侵入するウイルス・細菌から身を守る「自然免疫」と、侵入した異物を特定し排除する「獲得免疫」があります。ビタミンDはこの両方の免疫機能に関わっています。
- 免疫細胞(マクロファージ、T細胞、B細胞)の活性を調整
- 抗菌ペプチド「カテリシジン」の産生を促進し、感染防御を強化
- 過剰な炎症を抑える働き
これらにより、ビタミンDは免疫機能のバランスを整え、過剰な免疫反応や慢性炎症を防ぐと考えられています。
ビタミンD不足と感染症リスク
ビタミンD不足は、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるリスクが指摘されています。
2017年に医学誌「BMJ」に発表されたメタ解析では、ビタミンD補充により急性呼吸器感染症のリスクが全体として有意に低下したと報告されています(Martineau AR et al., 2017)。
また、ビタミンD濃度が低い人ほど感染症の発症率が高いことも複数の研究で示されています。
日本人に多いビタミンD不足の現状
厚生労働省による国民健康・栄養調査では、日本人の多くがビタミンDの推奨量を下回っているという報告があります。特に高齢者、女性、日光を浴びる時間の少ない人、デスクワーク中心の人では不足傾向が強いことが指摘されています。
ビタミンDの効果的な摂取方法
食事からの摂取
| 食品名 | 含有量の目安(μg/100g) |
|---|---|
| 鮭 | 39.0 |
| サンマ | 16.0 |
| しらす干し | 61.0 |
| 干し椎茸 | 17.0 |
特に魚類に豊富で、植物性食品ではきのこ類に含まれています。
日光浴
目安として、夏は10〜20分、冬は30分程度、手足に日光を当てるだけでも合成が促されます。
サプリメントを活用
血中ビタミンD濃度を効果的に保つには、1日10~20μg(400~800IU)程度が目安とされています。特に高齢者や日光不足の人ではサプリ活用が推奨されるケースがあります。
摂りすぎに注意すべきケース
脂溶性ビタミンのため、過剰摂取により高カルシウム血症のリスクがあります。腎疾患を持つ方や持病で薬を服用している方は医師に相談してください。
まとめ
ビタミンDは免疫機能を調整し、感染症の予防に役立つ可能性が示されている。
日本人の多くが不足しているとされ、日光不足や生活習慣が関係。
魚類、きのこ、日光浴、サプリなど複数の方法で補うことが重要。
過剰摂取には注意が必要。
参考文献・引用
Martineau AR, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. BMJ, 2017.
Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med, 2007.
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
日本人の食事摂取基準2020年版
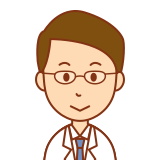
健康は資産、幸せは健康から!!

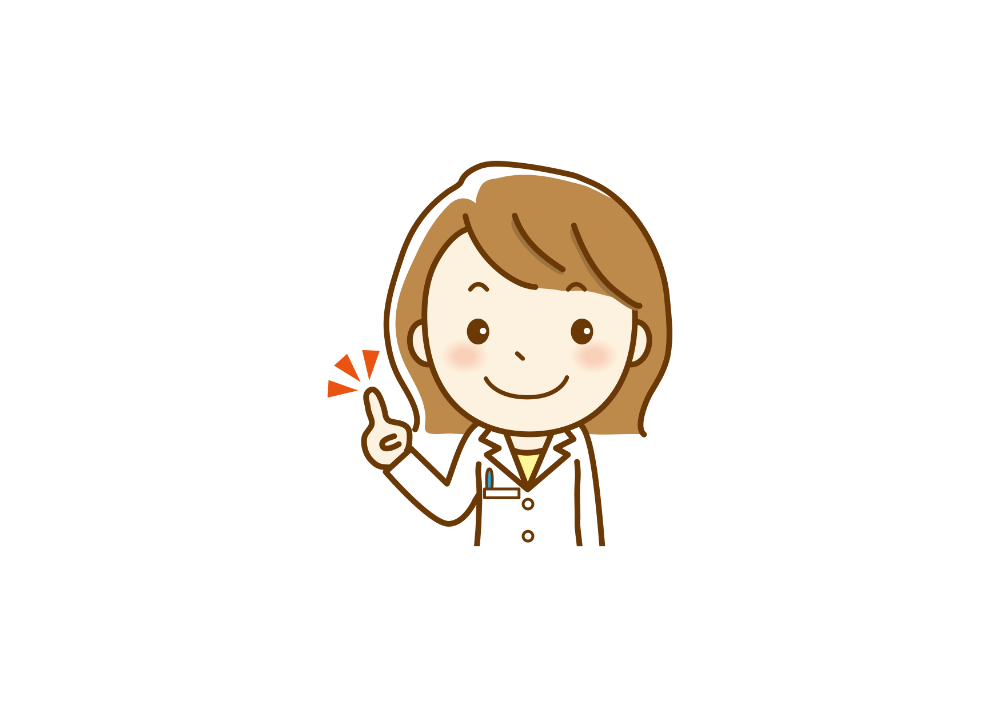


コメント