加齢とともに「もの忘れ」や「集中力の低下」が気になるという人は多いのではないでしょうか。そんな中、注目を集めているのが乳由来成分の「βラクトリン(ベータラクトリン)」です。
βラクトリンはミルク由来のペプチドで、脳の神経伝達に関わる働きをサポートすることが報告されています。本記事では、βラクトリンがどのように認知機能に関わるのか、最新研究の内容や摂取のポイントをわかりやすく紹介します。
βラクトリンが支える脳の健康:記憶力・集中力を助ける乳由来ペプチドの力
βラクトリンとは?
βラクトリンは、牛乳に含まれるたんぱく質「β-ラクトグロブリン」から作られるペプチド(たんぱく質が分解された小さな分子)です。日本の雪印メグミルク株式会社が研究開発を進め、特に認知機能への作用が注目されています。
この成分は、乳たんぱくを酵素で分解することで得られる「ラクトペプチド」の一種であり、脳の神経細胞の働きをサポートする可能性が報告されています。
βラクトリンと認知機能の関係
脳の神経細胞は、神経伝達物質を介して情報をやり取りしています。このネットワークがスムーズに働くことで、記憶力や注意力、判断力といった認知機能が維持されます。
βラクトリンには、脳内の「ドーパミン」や「アセチルコリン」といった神経伝達物質の働きを調整し、神経細胞間の情報伝達を助ける作用があると考えられています。
動物実験での知見
マウスを用いた研究では、βラクトリンを摂取した群で、記憶課題(迷路学習)を行った際に学習効率の改善がみられたと報告されています。この結果から、βラクトリンが脳の神経伝達に関わるシナプス機能をサポートする可能性が示唆されました。
ヒト臨床試験の報告
日本国内で行われた臨床試験では、健康な中高年者を対象にβラクトリンを12週間摂取させた結果、注意力や作業記憶(ワーキングメモリ)に関わる脳活動の改善が見られたとされています。
また、脳波測定によって前頭葉の活動が活性化する傾向が確認されており、これは「集中力の維持」や「情報処理の効率化」に関与していると考えられます。
βラクトリンの摂取方法
βラクトリンは牛乳由来の成分であり、一般的な食事ではごく微量しか摂取できません。そのため、サプリメントや機能性表示食品として摂取するのが現実的です。
日本では、βラクトリンを含む乳由来ペプチドが「機能性表示食品」として販売されており、「認知機能(注意力・記憶力)の一部を維持する」旨の表示が認められています。
例えば、1日1本のドリンクタイプや1包タイプの粉末サプリとして販売されており、継続的な摂取が推奨されています。
βラクトリンと他成分との相乗効果
βラクトリンは単独でも有用ですが、他の栄養素と組み合わせることで、より効果的に脳をサポートできる可能性があります。たとえば:
- DHA・EPA:脳の神経膜を構成し、情報伝達を円滑にする脂質
- ホスファチジルセリン:記憶や学習に関わる神経伝達の維持
- ビタミンB群:エネルギー代謝や神経機能をサポート
これらの成分をバランスよく摂取することで、脳の健康維持に役立つと考えられています。
注意点とまとめ
βラクトリンは安全性が高い成分ですが、乳由来のため、乳アレルギーのある方は注意が必要です。また、機能性表示食品であっても医薬品ではないため、病気の治療目的での使用は避けるべきです。
脳の健康を守るには、栄養だけでなく、睡眠・運動・社会的交流などの生活習慣も大切です。βラクトリンは、その中で「脳の働きを支えるサポート役」として期待できる成分と言えるでしょう。
参考文献・引用
Miyasaka, A. et al. “Effect of β-lactolin, a milk-derived peptide, on cognitive function in healthy adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Journal of Functional Foods, 2020.
雪印メグミルク株式会社「βラクトリンの研究紹介」
消費者庁「機能性表示食品 届出情報データベース」
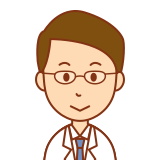
健康は資産、幸せは健康から!!




コメント