「最近、人の名前が出てこない」「集中力が続かない」と感じることはありませんか? こうした変化は加齢による自然なものですが、できる限りゆるやかにしたいものです。注目されているのが、青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸「DHA(ドコサヘキサエン酸)」と「EPA(エイコサペンタエン酸)」。これらは脳や神経の健康に深く関わり、認知機能の維持に役立つ可能性があると考えられています。本記事では、DHA・EPAと認知機能の関係を研究データとともにやさしく解説します。
DHA・EPAは記憶力や認知機能を守る?魚由来オメガ3の効果と摂取方法を解説
DHA・EPAとは?
DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、魚の油に多く含まれる「オメガ3脂肪酸」です。特に青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に豊富で、人の体内ではほとんど作ることができないため、食事やサプリメントから摂る必要があります。
DHAは脳や網膜の細胞膜に多く存在し、情報の伝達や学習、記憶に重要な役割を果たします。一方、EPAは血液をサラサラにし、炎症を抑える働きがあります。この2つは異なる特徴を持ちながら、互いに脳の健康を支える成分です。
DHA・EPAと認知機能の関係
研究では、DHA・EPAが次のように認知機能に関わることが報告されています。
- 神経細胞の柔軟性を保つ: DHAは脳の細胞膜を柔らかくし、情報伝達をスムーズにする。
- 炎症の抑制: EPAは炎症を抑え、脳の老化を遅らせる働きがある。
- 血流改善: DHA・EPAは血液の流れをよくし、脳に必要な酸素や栄養を届けやすくする。
これらの作用によって、記憶力や集中力の維持に役立つと考えられています。
研究からわかる効果
世界各国で行われた臨床研究では、DHA・EPAが認知機能に良い影響を与える可能性が示されています。
- 高齢者を対象とした研究では、DHAを多く摂っている人ほど認知症の発症リスクが低い傾向があると報告されています。
- アルツハイマー病の初期患者を対象にした試験では、DHA摂取が記憶力や思考の低下を遅らせる可能性があるとされました。
- 若年層でも、DHAを含む食事を摂ることで学習能力や集中力が高まったという報告があります。
ただし、研究によって結果が異なることもあり、「必ず効果がある」とは言い切れません。栄養素は薬ではなく、生活習慣全体と組み合わせて考える必要があります。
DHA・EPAを含む食べ物
DHA・EPAは魚に多く含まれています。特におすすめは以下の魚です。
- サバ
- イワシ
- サンマ
- アジ
- マグロ(特にトロ部分)
厚生労働省は、成人に1日あたり約1g程度のオメガ3脂肪酸をとることを推奨しています。これは、サバやイワシなら1切れ程度で補える量です。
サプリメントでの摂取
魚を毎日食べるのが難しい方は、サプリメントを利用するのも一つの方法です。DHA・EPAを含むサプリメントは、魚臭さを抑えた精製品が多く販売されています。
ただし、摂りすぎには注意が必要です。1日あたり3gを超えると、出血リスクが高まる可能性があると報告されています。医薬品や抗凝固薬を使用している方は、必ず医師に相談しましょう。
生活習慣と合わせて取り入れることが大切
DHA・EPAは単体で効果を発揮するというよりも、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動と組み合わせてこそ力を発揮します。
また、加工食品や肉の脂肪に多く含まれる「オメガ6脂肪酸」を摂りすぎると、オメガ3の効果が弱まるといわれています。揚げ物や加工食品を控え、魚やナッツ類を意識的に取り入れることがポイントです。
まとめ
DHA・EPAは、脳の健康を守る大切な栄養素であり、認知機能の維持に役立つ可能性があります。魚を食事に取り入れることで自然に摂取でき、難しい場合はサプリメントで補うのも良い方法です。研究でも一定の効果が示されており、日々の生活習慣と組み合わせて摂ることで、記憶力や集中力をサポートする可能性があります。今後の研究でさらに解明が進むことが期待されています。
参考文献(引用元)
Yurko-Mauro K, et al. “Beneficial effects of docosahexaenoic acid on cognition in age-related cognitive decline.” Alzheimers Dement. 2010.
Kotani S, et al. “Dietary supplementation of arachidonic and docosahexaenoic acids improves cognitive dysfunction.” J Lipid Res. 2006.
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
消費者庁 機能性表示食品 届出情報データベース
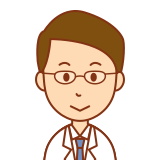
健康は資産、幸せは健康から!!

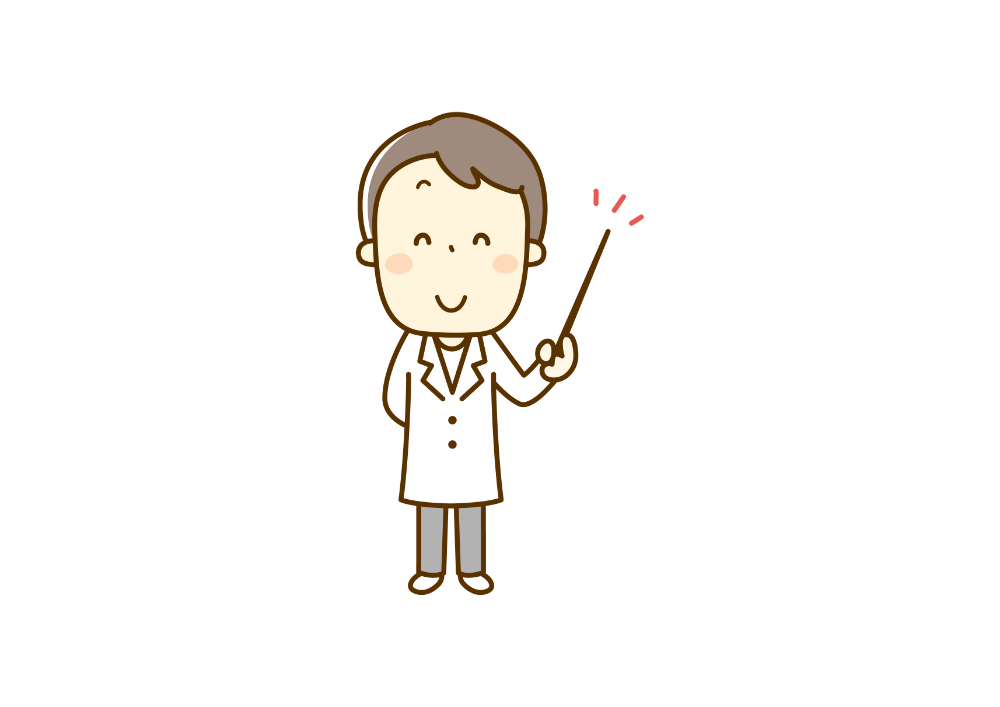


コメント