コレステロールが高めと指摘され、食生活の改善を意識している方も多いのではないでしょうか。そんな中、注目されているのが「難消化性デキストリン」。トクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品にも多く使われており、脂質の吸収を抑える成分として知られています。本記事では、難消化性デキストリンの基礎知識から、コレステロールに与える影響、摂取時の注意点まで、科学的根拠に基づいてわかりやすく解説します。
難消化性デキストリンはコレステロールを下げる?効果と注意点を徹底解説【機能性関与成分】
難消化性デキストリンとは?
難消化性デキストリンは、とうもろこし由来のデンプンを加熱・酵素処理して得られる水溶性食物繊維です。無味無臭で水に溶けやすく、飲料やサプリメント、ヨーグルトなどに広く利用されています。もともとは食物繊維不足を補う目的で開発されましたが、現在では血糖値や脂質、便通への効果が報告され、注目が集まっています。
コレステロールとは?
コレステロールは体内で細胞膜やホルモンを作るために欠かせない脂質の一種です。しかし、LDLコレステロール(悪玉)が増えすぎると動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まります。逆に、HDLコレステロール(善玉)は血管をきれいに保つ働きがあり、このバランスが重要とされています。
難消化性デキストリンとコレステロールの関係
複数の研究により、難消化性デキストリンにはコレステロールの吸収を抑える働きがあることが報告されています。特に、食事由来の脂質と胆汁酸の再吸収を抑制し、排泄を促すことで、LDLコレステロールの低下につながると考えられています。
臨床試験の例
例えば、2012年に発表された研究では、難消化性デキストリンを継続的に摂取することで、被験者のLDLコレステロール値が有意に低下したと報告されています[1]。また、食事に含まれる脂質の吸収を抑えるため、中性脂肪の上昇も抑える可能性があります。
機能性表示食品における位置づけ
日本では、難消化性デキストリンは「食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える」「おなかの調子を整える」といった機能性表示が許可されています。現在では、コレステロール改善目的での表示はされていないものの、間接的な脂質管理の補助として注目されています。
摂取方法と注意点
難消化性デキストリンは飲料に溶かして摂取するのが一般的で、1日5〜10g程度が目安とされています。しかし、摂りすぎると一時的な下痢やおなかの張りを感じることがあります。特に腸が敏感な方や持病のある方は、医師に相談のうえ使用することが推奨されます。
どんな人におすすめ?
- LDLコレステロールが高めと診断された方
- 脂っこい食事が多く、脂質管理に不安がある方
- 血糖値や中性脂肪の対策を同時に行いたい方
- 日常的に食物繊維が不足している方
医師や薬剤師との相談も重要
難消化性デキストリンはあくまで補助的な食品であり、医薬品の代わりにはなりません。コレステロール値が高く薬を服用している場合は、自己判断での使用を避け、必ず医師や薬剤師に相談してください。
まとめ
難消化性デキストリンは、水溶性食物繊維として腸内環境を整えるだけでなく、食事由来の脂質やコレステロールの吸収を抑える作用が報告されています。直接的なコレステロール低下をうたった食品は少ないものの、機能性表示食品として脂質代謝に着目した活用が進んでいます。日常的な食事のサポートとして、うまく取り入れていくことが大切です。
参考文献・引用
- 中村丁次監修『栄養学の基本がわかる事典』西東社, 2021年.
- 厚生労働省「食物繊維の摂取の現状」e-ヘルスネット.
- Watanabe Y, et al. “Effects of resistant maltodextrin on serum lipid levels and body fat in humans.” *Nutrition & Food Science*, 2012.
- 消費者庁 機能性表示食品データベース.
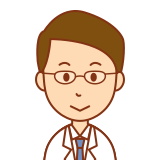
健康は資産、幸せは健康から!!




コメント