子どもが幼い頃から、「将来どれくらい教育費がかかるだろう?」と漠然と不安を抱えるご家庭は多いです。実際、大学進学まで含めると数百万円、場合によっては800万円以上かかるケースもあります。
本記事では、教育資金の「目安額」から、「いつからどのように貯めるか」「貯め方の方法(貯蓄・保険・投資)」「活用すべき公的制度」までを、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点も交えてわかりやすく解説します。悩まず、着実に準備を進めるための実践ガイドとしてご活用ください。
子どもの教育資金を安心準備|必要額・貯め方・活用制度をFPが徹底解説
1. 教育資金はいくら必要?目安額と費用の構成
教育資金を準備する上で、まず「どれくらいかかるか」を把握することが重要です。例えば、日本政策金融公庫のデータによると、大学(入学金+4年間在学費用)で、国公立で約 481万円、私立文系で約 690万円、私立理系で約 821万円という結果が出ています。
また、高校までの学費・塾代・習い事・受験費用なども含めると、トータルで早期には数百万円~一千万円近くになる家庭もあるため、早めの準備がカギです。
2. いつから準備を始めるべき?早期スタートの重要性
教育資金を貯める上では「期間(時間)」が強みになります。例えば、幼児期からコツコツ積み立てられれば少額で備えられる可能性が高まります。
反対に、準備を遅らせると月々の積立額が大きくなったり、リスクを取らざるを得ない運用を検討せざるを得ないケースも出てきます。早期スタートこそが安心への第一歩です。
3. 教育資金の貯め方―貯蓄・保険・投資の3つの選択
資金準備の方法として代表的なのは以下の3つです。
3.1 貯蓄(預金・積立)
最も安心できる方法ですが、利回りは低めです。例えば、普通預金や定期預金を自動積立にすることで、引き出しを抑えて貯めることができます。
3.2 学資保険・貯蓄型保険
教育時期にあわせて給付金が出るタイプの保険。保障も兼ねているので安心ですが、運用利回り・保障料・長期契約という点の理解が必要です。
3.3 投資・積立投資信託(NISAなど)
長期・時間を味方にできるなら、運用を活用して準備を加速する選択肢もあります。例えば、つみたてNISAなども活用可能です。
4. 貯め方の比較:メリット・注意点
各手法にはメリット・デメリットがあります。家庭の状況・リスク許容度によって選択すべき方向が変わります。
- 貯蓄:リスクが低い/インフレに弱い
- 学資保険:保障を兼ねられる/払い込み期間・元本割れリスクあり
- 投資:期待リターンあり/リスク・元本変動あり、時間の確保が重要
5. FP視点での“賢い教育資金準備”の設計ポイント
ファイナンシャルプランナーとして、次のような視点で設計することをおすすめします。
5.1 家計から捻出できる毎月の金額を見える化
「毎月いくら積めるか」を家計から逆算し、無理なく継続できる金額を決めましょう。
5.2 目標金額・時期を明確に設定
例えば「18歳時点で〇〇万円必要」と設定し、いつから何円ずつ貯めるかを逆算します。
5.3 分散と併用を意識する
貯蓄・保険・投資を併用し、バランスよく備える設計が望まれます。
5.4 途中で見直す習慣を持つ
子どもの成長、家計状況、進路変更など変化に応じて定期的に見直しましょう。
6. 公的制度・制度活用も忘れずに
教育資金の負担軽減には公的制度の活用も重要です。例えば、高校生等奨学給付金制度(非課税世帯対象)や、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置などがあります。
まとめ
教育資金の目安は、大学まで進学する場合数百万円~800万円超になる可能性があります。
早めに準備をスタートし、時間を味方にすることがカギです。
貯蓄・保険・投資という複数の方法を状況に応じて使い分け・併用することが有効です。
ファイナンシャルプランナーとしては、「家計に無理ない積立額」「目標金額・時期の明確化」「分散・併用」「定期的な見直し」が重要な設計ポイントです。
公的制度や贈与税非課税措置なども活用し、準備をより効率的に進めましょう。
参考文献・引用元
日本FP協会「ストレスフリーな教育資金準備」
インズウェブ「子どもの教育資金を貯めるには?貯め方診断であなたに合った方法」
白書ポルト「子どもの教育費、どう準備する?」
投信プラザ「教育資金のいくらかかる?準備の仕方や足りない時の対応策を解説」
富国生命「教育資金、家庭に合う貯め方で今から“子どもの将来”」
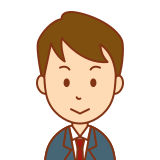
今日が一番若い日




コメント