カレーの黄色い色素として知られる「クルクミン」。ウコン(ターメリック)に含まれる成分で、古くから健康維持に役立つとされてきました。近年はその抗酸化作用や抗炎症作用に注目が集まり、特に脳の健康や認知機能をサポートする可能性が研究で示されています。この記事では、クルクミンと認知機能の関係を、研究結果や体験談を交えてわかりやすく解説します。
クルクミンは記憶力や認知機能をサポートする?研究と効果、安全性をやさしく解説
クルクミンとは?
クルクミンは、ショウガ科の植物「ウコン(ターメリック)」に含まれる黄色い色素成分です。カレー粉の主要な成分として知られています。古来よりインドや中国では、消化を助けるスパイスや薬草として利用されてきました。
近年は、その抗酸化作用や抗炎症作用が科学的に注目され、生活習慣病や脳の健康に関連する研究が数多く行われています。
なぜクルクミンが認知機能に良いとされるのか?
認知機能は「記憶する」「考える」「判断する」など脳の働きを支える力のことです。加齢やストレス、酸化ダメージなどによって衰えやすい特徴があります。
クルクミンが注目される理由は以下の通りです。
- 抗酸化作用: 脳細胞を酸化ストレスから守る。
- 抗炎症作用: 神経の炎症を抑え、情報伝達をスムーズにする。
- アミロイドβの蓄積抑制: 認知症と関連する物質の蓄積を防ぐ可能性。
- 神経細胞の保護: 記憶や学習を担う脳の部位に働きかける。
研究で示されている効果
クルクミンの認知機能に対する研究は世界各地で行われています。
- アメリカの研究では、60歳以上の健常者がクルクミンを18か月間摂取したところ、記憶力テストと注意力テストで改善が見られました。
- インドの疫学調査では、カレーをよく食べる高齢者は認知機能テストの成績が高い傾向にあることが示されています。
- 動物実験では、クルクミンが脳内の炎症を抑え、神経の保護に働くことが報告されています。
ただし、すべての研究で効果が確認されているわけではなく、個人差が大きい点には注意が必要です。
クルクミンの吸収性の課題
クルクミンは健康に役立つ成分ですが、体内での吸収率が非常に低いという課題があります。そのため、効率的に摂取するには以下の工夫が有効とされています。
- 黒コショウに含まれる「ピペリン」と一緒に摂ることで吸収率が上がる。
- 脂溶性なので、油と一緒に調理すると体に取り込みやすくなる。
- サプリメントでは「ナノ化クルクミン」など吸収性を高めた製品がある。
体験談
物忘れが気になり始めた50代のころから、クルクミンサプリを試しました。最初の1〜2週間はあまり変化を感じませんでしたが、1か月ほど続けると、会議中に話の流れをスムーズに追えるようになった感覚がありました。気分も前向きになり、疲れにくさを感じたのも印象的でした。
もちろんこれは個人の体験であり、すべての人に当てはまるわけではありませんが、食生活やサプリメントが「脳のコンディション」に影響することを実感しました。
安全性と注意点
クルクミンはスパイスとして長い歴史を持つため、比較的安全性の高い成分といえます。ただし、注意すべき点もあります。
- 大量摂取すると消化不良や下痢を起こすことがある。
- 胆石や胆嚢の疾患がある人は医師に相談する必要がある。
- 抗凝固薬を使用している人は相互作用の可能性に注意。
日常生活での取り入れ方
クルクミンを摂取する方法は主に以下の2つです。
- 食事: カレーやウコンを使った料理で自然に摂取できる。
- サプリメント: 吸収性を高めた製品で効率よく摂れる。
毎日の食生活に少しずつ取り入れることが、無理なく続けるコツです。
まとめ
クルクミンは抗酸化作用や抗炎症作用を持ち、脳の健康や認知機能をサポートする可能性があります。研究では記憶力や注意力への良い影響が報告されており、食事やサプリで取り入れることが可能です。ただし、吸収率の課題や体質による違いがあるため、過度な期待は禁物です。バランスのとれた生活習慣と組み合わせることで、より健康的な脳を維持できるでしょう。
参考文献(引用元)
Small GW, et al. “Memory and Brain Amyloid and Tau Effects of a Bioavailable Form of Curcumin in Non-Demented Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled 18-Month Trial.” Am J Geriatr Psychiatry. 2018.
Ng TP, et al. “Curry consumption and cognitive function in elderly Singaporeans.” Am J Epidemiol. 2006.
日本認知症学会「認知症予防に関するガイドライン」
厚生労働省 e-ヘルスネット「抗酸化物質と健康」
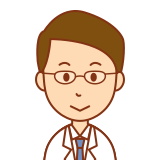
健康は資産、幸せは健康から!!




コメント