寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝起きても疲れが取れない――現代人の多くが抱える睡眠の悩み。近年、肝機能サポート成分として知られてきた「オルニチン」が、睡眠の質改善にも関与する可能性が注目されています。オルニチンはシジミなどに多く含まれるアミノ酸で、疲労回復やストレス軽減を通じて、快適な睡眠を助けると考えられています。本記事では、オルニチンと睡眠の関係、最新研究での知見、安全性や摂取方法について詳しく解説します。
オルニチンは睡眠の質を改善する?研究でわかる効果と安全な摂取方法
オルニチンとは?
オルニチンは体内で自然に生成される非必須アミノ酸のひとつです。特に肝臓の代謝経路である「尿素回路」に関与し、アンモニアを解毒する役割を果たしています。シジミやヒラメ、マグロ、エノキダケなどに豊富に含まれており、健康食品やサプリメントとしても利用されています。
オルニチンと睡眠の関係
オルニチンは直接的に「睡眠ホルモン」を生成するわけではありませんが、以下のような経路で睡眠の質に影響を与えると考えられています。
- ストレス軽減作用:コルチゾール分泌を調整し、ストレスによる覚醒を抑制する。
- 疲労回復の促進:肝臓の解毒作用を助け、疲労感を軽減する。
- リラックス効果:副交感神経を優位にし、入眠を助ける。
研究で報告されている効果
いくつかの臨床試験で、オルニチンの摂取が睡眠に良い影響を与えることが示されています。
- ストレスの軽減:健常成人を対象とした研究で、オルニチン摂取により起床時のストレスホルモン(コルチゾール)の低下が観察されました。
- 睡眠の質改善:オルニチン摂取群では「熟睡感」や「翌朝の疲労感」が改善したと報告されています。
- 肝機能サポート:飲酒や疲労により負担を受けた肝臓をサポートすることで、間接的に睡眠の質が高まる可能性があります。
作用メカニズム
オルニチンが睡眠に寄与するとされるメカニズムは主に以下の通りです。
- アンモニアの解毒作用:体内のアンモニア濃度が高いと疲労や不眠の原因となります。オルニチンは尿素回路を活性化し、アンモニアを尿素に変換して排泄を促します。
- ストレスホルモンの調整:オルニチンは副腎皮質ホルモンの分泌を調整し、睡眠を妨げる過剰なストレス反応を抑えます。
- 自律神経バランスの改善:交感神経の過剰な興奮を抑制し、副交感神経を優位にすることで入眠をサポートします。
オルニチンを含む食品とサプリメント
オルニチンを豊富に含む代表的な食品は「シジミ」です。特に冷凍シジミには含有量が多く、100gあたり約10〜15mg程度含まれています。ただし、研究で用いられる有効量(数百mg〜数g)を食品から摂取するのは難しいため、サプリメントの活用が一般的です。
摂取量の目安
臨床研究では1日400〜800mg程度のオルニチン摂取で睡眠改善効果が報告されています。サプリメントとしては、就寝前または夕方以降の摂取が推奨されることが多いです。
安全性と副作用
オルニチンは食品由来のアミノ酸であり、安全性が高いとされています。これまでの研究で大きな副作用は報告されていません。ただし、高用量での摂取に関しては十分なデータがないため、サプリメントを利用する場合は表示されている目安量を守ることが大切です。
生活習慣との組み合わせ
オルニチンの効果を最大限に活かすには、以下のような睡眠衛生の工夫が欠かせません。
- 就寝前のスマホやPC使用を控える
- 寝室環境を暗く静かに整える
- 就寝直前のアルコールやカフェインを避ける
- 日中の適度な運動を習慣化する
こうした工夫とオルニチンの摂取を組み合わせることで、より高い睡眠改善効果が期待できます。
まとめ
オルニチンは肝機能サポートや疲労回復に加え、ストレス軽減や自律神経調整を通じて睡眠の質を改善する可能性があります。食品からの摂取も可能ですが、有効量を得るにはサプリメントが有用です。安全性も高く、日常生活の工夫と併用することで、より快適な眠りをサポートしてくれるでしょう。
参考文献(引用元)
Takeda H, et al. “Effects of oral ornithine on stress and sleep quality.” Nutr J. 2014.
日本栄養・食糧学会誌「オルニチンの生理作用」.
厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣」.
Yamamoto K, et al. “Ornithine supplementation and fatigue recovery.” J Nutr Sci Vitaminol. 2010.
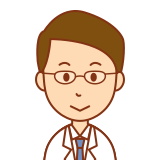
健康は資産、幸せは健康から!!

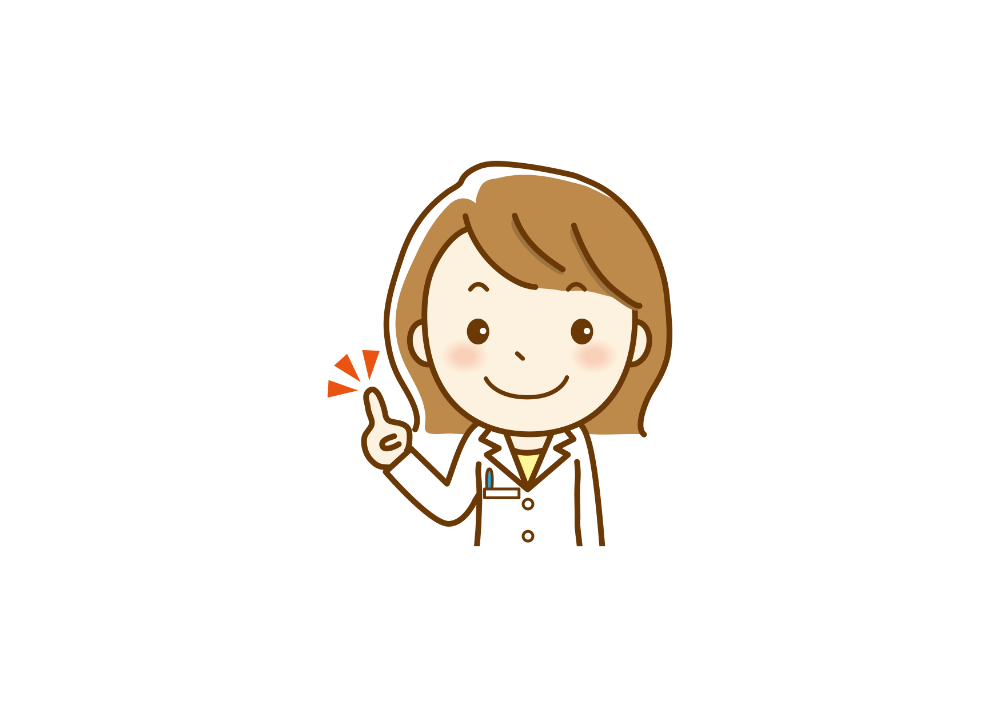

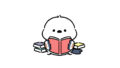
コメント