高血圧は、日本人の3人に1人が抱えているとされる生活習慣病の一つです。放置すると心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こすリスクが高まるため、日頃のケアが欠かせません。最近では、特定の食品成分「ペプチド」に高血圧予防への効果が期待され、注目が集まっています。この記事では、ペプチドとは何か、高血圧にどのような作用をもたらすのか、科学的根拠を交えてわかりやすく解説します。
血圧が高めの方へ|ペプチドの効果と注目成分とは?
ペプチドとは?
ペプチドとは、アミノ酸が2つ以上つながった化合物で、タンパク質が分解されてできる成分です。食品の中でも、乳製品、大豆、魚、かつお節などのタンパク質を含む食材を酵素で分解することで得られます。ペプチドは体内で様々な生理作用を発揮し、最近では「機能性表示食品」の成分としても使われるようになっています。
高血圧とペプチドの関係
高血圧の主な原因の一つは、血管を収縮させるホルモン「アンジオテンシンII」の過剰生成にあります。この生成を助けるのが酵素「アンジオテンシン変換酵素(ACE)」です。ある種のペプチドは、このACEの働きを阻害する作用があることが報告されており、結果的に血管を広げて血圧を下げるとされています。
ACE阻害作用を持つ代表的なペプチド
- ラクトトリペプチド(VPP・IPP):乳たんぱく質由来のペプチド。多数の臨床研究で降圧作用が示されており、特定保健用食品(トクホ)としても認可されています。
- 大豆ペプチド:大豆たんぱく質を酵素処理して得られる。動物実験やヒト試験で血圧低下作用が報告されています。
- 魚由来ペプチド(イワシペプチドなど):イワシやサケなどの魚のタンパク質を酵素分解して得られる。ACE阻害活性が確認されています。
ヒトでの効果は?科学的エビデンスを紹介
以下は、ヒト試験で確認されたペプチドの血圧低下作用の一例です。
- ラクトトリペプチド(VPP・IPP):収縮期血圧(上の血圧)が軽度高めの成人において、約8週間の摂取で平均4〜5mmHgの降圧効果が確認されました(Mizuno et al., 2004)。
- イワシペプチド:収縮期血圧が高めの中高年男女に対し、12週間の摂取で血圧の有意な低下が認められました(Nakamura et al., 2009)。
どのように摂取すればよい?
ペプチドは、自然な食品から摂取するほか、加工食品やサプリメントとしても販売されています。市販の「血圧が高めの方に」と表示されたトクホや機能性表示食品を選ぶことで、一定量の有効成分を継続的に摂取できます。
ただし、摂取の目安量や効果の出方には個人差があり、過剰摂取や医薬品との併用には注意が必要です。特に降圧薬を服用中の方は、事前に医師や薬剤師に相談しましょう。
注意点と副作用について
ペプチドは基本的に安全性が高いとされていますが、以下の点には注意が必要です。
- 降圧薬との併用で、血圧が下がりすぎる可能性がある
- 乳アレルギー、大豆アレルギーのある方は、原材料に注意
- 過剰摂取による健康被害のリスクは低いが、適量を守ることが大切
ペプチドは高血圧対策の「補助」として有効
ペプチドは、高血圧の予防や軽減に役立つ可能性を持つ食品成分です。ACE阻害作用を持つことから、血圧を自然にコントロールする働きが期待されています。ただし、あくまで補助的な役割であり、日々の生活習慣(減塩、適度な運動、体重管理)と併せて取り入れることが重要です。
まとめ
ペプチドは、乳製品や大豆、魚などのタンパク質から得られる成分で、血圧を下げる作用が期待される機能性成分です。特にACE阻害作用によって血管の収縮を抑え、血圧を下げる働きがあるとされ、多くの研究でもその効果が支持されています。健康診断で血圧が高めと指摘された方や、家族に高血圧の方がいる場合は、毎日の食事にペプチドを取り入れることを検討してみてください。ただし、サプリメントなどでの過剰摂取や、薬との相互作用には十分な注意が必要です。
参考文献・引用
- Mizuno S, et al. (2004). Antihypertensive effect of casein-derived tripeptides in hypertensive subjects. Am J Clin Nutr. 80(4): 683–691.
- Nakamura Y, et al. (2009). Effect of sardine peptides on blood pressure in mild hypertensive subjects. Hypertens Res. 32(6): 488–493.
- 独立行政法人 国立健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」
- 消費者庁 機能性表示食品データベース
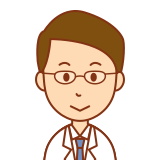
健康は資産、幸せは健康から!!

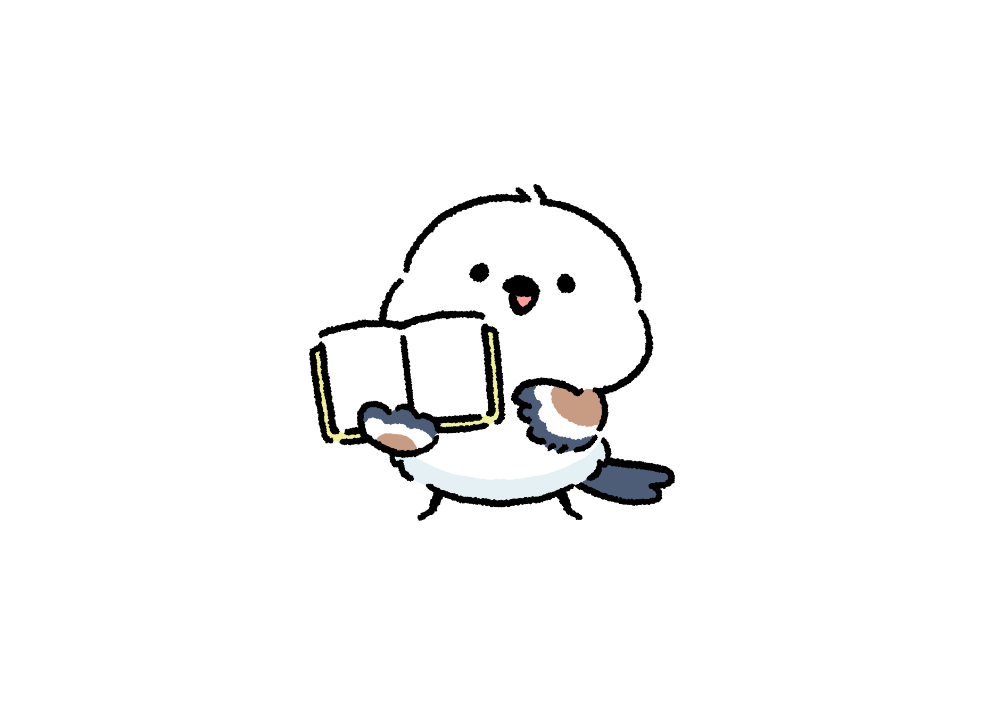


コメント