コレステロールが気になる方にとって、植物ステロール(フィトステロール)という成分を耳にしたことがあるかもしれません。最近では、「植物ステロール配合」のヨーグルトやマーガリンなどの食品も注目を集めています。しかし、植物ステロールは本当にコレステロール値を下げるのでしょうか?この記事では、植物ステロールの作用メカニズムや摂取による効果、安全性、摂取時の注意点について、エビデンスをもとにわかりやすく解説します。
植物ステロールがコレステロールを下げる?その効果と注意点を解説
植物ステロールとは?
植物ステロール(フィトステロール)は、植物に含まれるステロールの一種で、構造が人間のコレステロールに非常によく似ています。主に植物油、ナッツ、豆類、穀物などに含まれており、近年では「コレステロールを下げる機能性成分」として、特定保健用食品や機能性表示食品にも活用されています。
コレステロールの吸収を妨げる仕組み
植物ステロールの最大の特徴は、腸管でのコレステロールの吸収を抑える働きにあります。腸内では、食事から摂取したコレステロールと胆汁由来のコレステロールがミセル(小さな脂質の粒子)という形で吸収されますが、植物ステロールはこのミセルに競合的に取り込まれることで、コレステロールの吸収を抑制します。
結果として、血中のLDL(悪玉)コレステロール値を下げる効果があるとされており、心血管疾患のリスク低減にもつながる可能性があります。
どれくらいの量で効果があるのか?
研究によると、1日あたり1.5g〜3gの植物ステロールを継続的に摂取することで、LDLコレステロールを約7〜10%程度低下させる効果が確認されています。
たとえば、植物ステロールを配合したヨーグルトやマーガリンなどでは、1製品に約0.8〜2.0g程度の植物ステロールが含まれており、1日1〜2回の摂取で効果的な量に達する設計になっている場合が多いです。
植物ステロールの安全性と注意点
植物ステロールは通常の食品に含まれる成分であり、適量であれば安全とされています。しかし、以下のような注意点もあります。
- 高用量摂取は意味がない:摂取量を増やしても、3g/日以上では効果が頭打ちになるとされており、過剰摂取のメリットはありません。
- 脂溶性ビタミンの吸収への影響:脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)の吸収が一時的に低下する可能性があるため、バランスのよい食事を心がけることが重要です。
- シトステロレミアの人は要注意:まれな遺伝性疾患「シトステロレミア(シトステロール血症)」の方は植物ステロールを多く吸収してしまうため、摂取は避けるべきです。
植物ステロール配合食品の例
以下のような食品に植物ステロールが添加されていることがあります。
- 植物ステロール配合ヨーグルト
- 植物ステロール入りマーガリン
- 植物ステロール配合チーズ風味食品
パッケージには「コレステロールが気になる方へ」「LDLコレステロールを下げる」などの表示がされており、機能性表示食品として販売されています。
医薬品との併用に注意が必要?
スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)などの脂質異常症治療薬を使用している方は、医師や薬剤師に相談のうえで植物ステロール配合食品を取り入れるようにしましょう。植物ステロールはスタチンとの併用で相乗効果を示すこともありますが、個々の体質や病状によって異なります。
まとめ:植物ステロールはコレステロール対策の味方
植物ステロールは、コレステロールの吸収を抑えることで、LDLコレステロール値の低下に寄与する成分です。1日1.5〜3gの摂取を目安に、機能性表示食品などを活用することで、食生活の中で無理なく取り入れることが可能です。ただし、脂溶性ビタミンの吸収への影響や特定の疾患との関係にも留意しながら、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
参考文献
- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版
- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. (2010). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to plant sterols and plant stanols. EFSA Journal, 8(10), 1813.
- U.S. Food & Drug Administration (FDA). Health Claim Notification for Phytosterols and Risk of Coronary Heart Disease.
引用
- 「植物ステロールがコレステロールの吸収を抑える」: EFSA Journal, 2010
- 「1.5〜3gでLDL-Cを約10%低下」: 日本動脈硬化学会ガイドライン(2022年版)
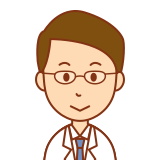
健康は資産、幸せは健康から!!




コメント